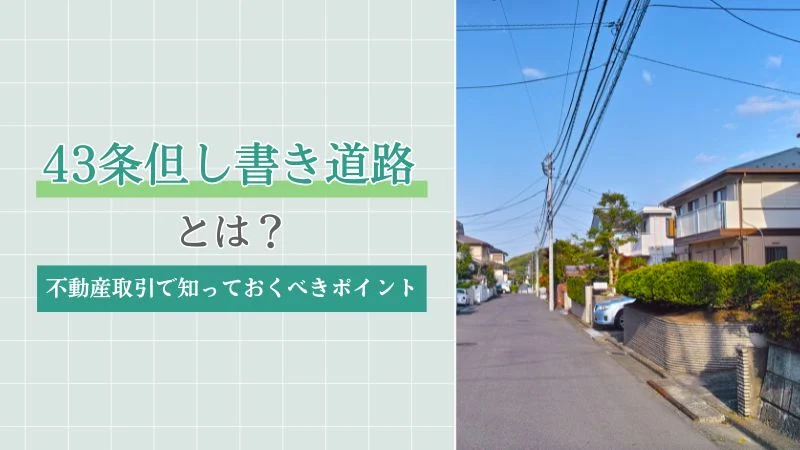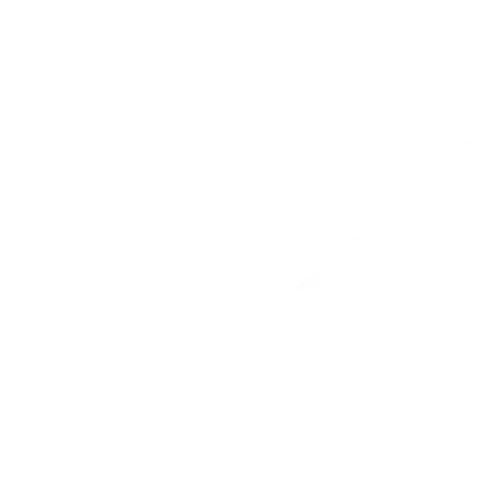不動産取引で「43条但し書き道路」という言葉を目にしたことがないでしょうか。
43条但し書き道路に面した建物は、建築制限や資産価値の面で予想外の問題に直面する可能性があります。
本記事では、43条但し書き道路とはどういうものなのか、そしてどのような注意点があるのかについて解説します。
43条但し書き道路とは

43条但し書き道路とは、建築基準法第43条第1項の但し書きに基づき、一定の条件を満たす場合に例外的に建築許可を認める道路のことです。
建築基準法では原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。
しかし現実問題として法的な道路に接していない土地や、接道要件を満たさない土地が数多く存在しているのが実情です。
このような土地では、周囲の環境や安全性、利便性を総合的に判断して、特定行政庁が「建築基準法上の道路と同等の機能を有する」と認めた場合に限り、建築が許可されます。
これが43条但し書きの許可制度であり、この許可を受けた通路や道が43条但し書き道路と呼ばれています。
具体的には、幅員が4メートル未満の通路や、建築基準法施行前から存在する道、開発行為によって生まれた通路などが対象となります。
例えば、昭和の住宅地によく見られる幅3メートル程度の細い道や、農道として使われていた通路が住宅地として開発された際に認定されるケースなどです。
ただし、単に通路があるだけでは認定されず、建築主が個別に申請を行い、行政の厳格な審査を経て初めて建築許可が下りる仕組みになっています。
43条但し書きの許可が認められるために何が必要?

43条但し書きの許可が認められるためには、複数の厳格な条件を満たす必要があります。
まず基本的な要件として、その通路が建築物の利用に支障がなく、かつ避難や通行の安全性が確保されていることが求められます。
具体的には、通路の幅員が建築物の規模や用途に対して適切であること、行き止まりの場合は奥行きに制限があること、通路の舗装状況や排水設備が整備されていることなどが審査されます。
安全性の観点では、緊急車両のアクセスが可能かどうかも重要な判断基準となります。
消防車や救急車が接近できない立地では、建築物の用途や規模に厳しい制限が課せられる場合があります。
また、通路の維持管理が適切に行われる見込みがあるかどうかも審査の対象となり、私道の場合は所有者や管理者との協定書の提出が求められることもあります。
そして周辺の土地利用状況や都市計画上の位置づけも考慮されます。
住宅地として適切な環境が整っているか、将来的な道路整備計画との整合性があるかなども審査のポイントです。
これらの条件をクリアしたとしても、許可は個別の建築計画に対して与えられるものであり、土地そのものに恒久的な建築権が付与されるわけではありません。
つまり、将来建て替えを行う際には、改めて同様の審査を受ける必要があり、その時点での基準や周辺環境の変化によって許可が下りない可能性もあることを理解しておく必要があります。
43条但し書き道路に面した建物の問題点

43条但し書き道路に面した不動産には、一般的な道路に面した物件とは異なる重要なリスクが存在します。
これらのリスクを事前に理解しておかなければ、購入後に予期せぬ問題に直面する可能性があります。
建築制限に関するリスク
最も深刻なリスクは、将来の建築制限です。
43条但し書きの許可は、あくまで個別の建築計画に対して与えられるものであり、土地に恒久的な建築権を保証するものではありません。
現在の建物を将来建て替える際には、改めて特定行政庁の許可を取得する必要があります。
この際、建築基準法の改正や周辺環境の変化、行政の判断基準の厳格化などにより、以前は認められていた建築が認められなくなる可能性があります。
実際に、過去に許可を得て建築された住宅であっても、建て替え時に同等の規模での再建築が認められないケースが発生しています。
最悪の場合、建て替え自体が認められず、既存建物の維持修繕のみしか許可されない状況も考えられます。
また、建築できる建物の用途や規模にも制限が課される場合があります。
住宅以外の用途への変更が制限されたり、建物の高さや床面積に厳しい制約が設けられるといったことです。
この制限あることで家族構成の変化や、生活スタイルの変更に対応した増改築が困難になる可能性があります。
資産価値への影響
43条但し書き道路に面した不動産は、資産価値の面でも大きなリスクを抱えています。
例えば金融機関の住宅ローン審査では、将来の建て替えリスクや再販売時の流動性を重視するため、43条但し書き道路の物件に対しては融資条件が厳しくなる傾向があります。
融資額の減額や金利の引き上げ、担保評価の大幅な減額などが行われることが一般的です。
売却時にも同様の問題が生じます。
購入希望者の多くは住宅ローンを利用するため、融資が困難な物件は買い手が見つかりにくく、結果として売却価格の下落や売却期間の長期化につながります。
不動産業者からも敬遠されがちで、積極的な販売活動が期待できない場合もあります。
さらに建築制限により将来の建て替えが困難になった場合、建物の老朽化とともに資産価値が大幅に下落するリスクがあります。
一般的な不動産では土地の価値が維持されるため建物が古くなっても一定の資産価値を保てますが、建て替えができない土地では更地にしても活用方法が限定されるため、資産価値の回復が困難です。
43条但し書き道路に面した物件の処分方法
43条但し書き道路に接する物件の売却を検討している場合、主に2つの方法があります。
隣接地の所有者への売却、または専門買取業者への相談が、現実的な選択肢となるでしょう。
隣接地所有者への売却を検討する
43条但し書き道路に接する物件は建築基準法の制約があり、一般市場では買い手を見つけにくいのが実情です。
しかし、隣接地の所有者にとっては、所有地を拡張できる魅力的な機会となるため、購入意欲を示すケースが少なくありません。
隣接地所有者が二世帯住宅の建築や駐車スペースの拡張を計画している場合、交渉が円滑に進む可能性が高まります。
ただし、価格面での合意形成や契約条件の調整が難航することもあります。
こうした課題を避けるため、個人間での直接交渉ではなく、不動産業者に仲介を依頼することをおすすめします。
専門家を介することで、価格交渉から契約締結、登記手続きまで適切に進められます。
専門買取業者への相談
隣接地への売却が困難な場合は、訳あり物件を扱う専門買取業者への相談も検討してみてください。
43条但し書き道路に接する土地は再建築に制限があるため、一般的な仲介売却には時間を要しますが、買取業者なら現状のまま速やかに現金化できます。
買取価格は市場相場を下回る傾向にありますが、売却できないまま固定資産税の負担が続く状況や、管理責任を負い続けるリスクを回避できる点はメリットです。
まとめ
43条但し書き道路は、建築基準法上の特殊な制度により認定された道路のことです。
現在建築が可能であっても将来の建て替え時には改めて許可が必要で、その許可が保証されていないこと、また、融資の制約や資産価値への影響など、経済的なリスクは無視できません。
リスクを十分に理解した上で適切な価格で取引が行われるなら、43条但し書き道路に面した物件も有効な選択肢となり得ます。
不動産は人生で最も高額な買い物の一つです。43条但し書き道路に関わる取引では、特に慎重な判断と専門的な調査を心がけましょう。
INTERIQでは、お客様の状況や物件の特性を把握し、最適なご提案をいたします。お見積もり・ご相談は無償で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。