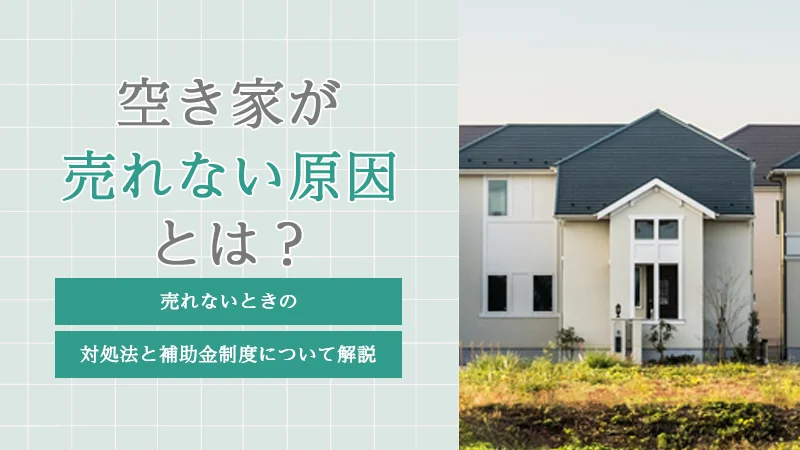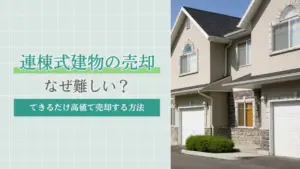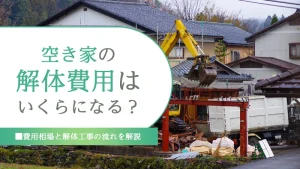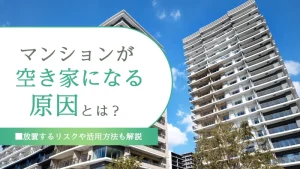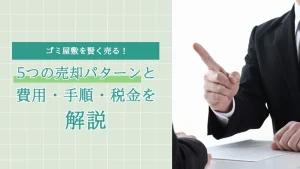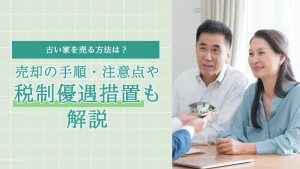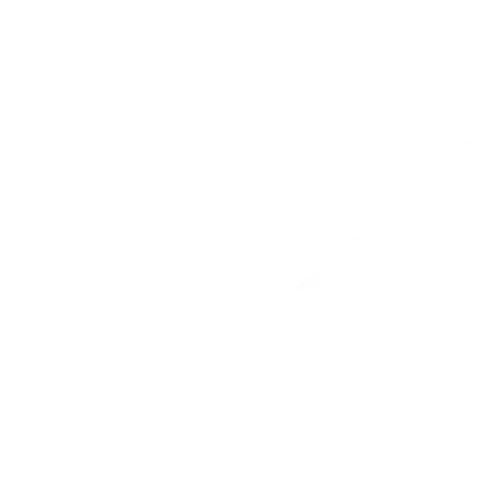所有している空き家がなかなか売れず、固定資産税の負担や管理の手間に悩んでいませんか。
親から相続した実家を売りに出しても買い手が見つからない、不動産会社に相談しても納得のいく提案がもらえない、そんな悩みを抱える方は少なくありません。
この記事では、空き家が売れにくい主な原因から、具体的な解決策、放置することで生じるリスク、そして活用できる補助金制度までを、わかりやすく解説します。
空き家が売れない理由
空き家がなかなか売れないのには、いくつかの明確な理由があります。
まずは、自分の物件がどの理由に当てはまるのかを客観的に把握することが、スムーズに売却を進めるために大切です。
立地条件がよくない
空き家が売れにくい大きな理由のひとつが「立地条件の悪さ」です。
最寄り駅やバス停から遠い場所にあったり、スーパー・病院・学校など生活に必要な施設が近くにない地域では、購入希望者が集まりにくくなります。とくに、駅まで徒歩15分以上かかる物件や、車がないと生活が難しいエリアの空き家は、買い手を見つけにくい傾向があります。
国土交通省の調査によると、中古住宅の購入者の約半数が「立地環境のよさ」を重視していることが分かっています。通勤や通学のしやすさ、買い物の利便性などは、多くの人にとって「住みやすさ」を判断するうえで重要なポイントです。
さらに、海抜の低い地域や土砂災害警戒区域に指定されている場所、インフラ整備が十分でない地域も、買い手から敬遠されやすい傾向があります。
出典:国土交通省「令和4年度住宅市場動向調査報告書」(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610299.pdf)
建物の状態が悪い
建物の老朽化が進んでいる空き家は、買い手が見つかりにくい代表的なケースです。
雨漏りや壁のひび割れ、床の傾き、シロアリ被害などの不具合がある建物は、購入後に高額な修繕費が発生する可能性があるため、多くの人が購入をためらいます。とくに築30年以上の物件ではこうした劣化が目立ちやすくなります。
また、建物の耐震性も重要な判断基準です。昭和56年(1981年)以前に建てられた旧耐震基準の住宅は、現在の耐震基準を満たしていないため、地震への不安から買い手がつきにくくなります。
さらに、長期間人が住んでいない空き家は、湿気やカビ、換気不足による腐食など、見えない部分でダメージが進んでいることもあります。見た目はきれいでも、実際には建物の劣化が深刻化しているケースも少なくありません。
再建築不可で建て替えができない
「再建築不可物件」と呼ばれる空き家は、売却がとくに難しいケースのひとつです。
建築基準法では、新しく建物を建てるためには「幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」が条件とされています。この条件を満たしていない土地では、たとえ今ある建物を解体しても、新しい建物を建てることができません。
昭和25年以前に建てられた家屋の多くは、当時は現在の建築基準法が施行されていなかったため、接道条件を満たしていないケースが少なくありません。
再建築不可の土地は、建物が老朽化しても建て替えができないという大きな制約があります。さらに、地震や災害で倒壊した場合も新築が認められないため、一般の購入希望者はリスクを感じやすく、結果として売却が非常に難しくなる傾向があります。
出典:国土交通省「接道規制のあり方について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001894185.pdf)
隣の土地と境界が曖昧
隣の土地との境界線があいまいな空き家は、売却がスムーズに進まない原因になります。
境界が不明確なまま売却すると、購入後に隣地の所有者とトラブルになるおそれがあります。買い手にとってはリスクが高いため、境界が確定していない物件は敬遠されやすい傾向があります。
境界を正式に確定するには、土地家屋調査士などの専門家に依頼して測量を行う必要があります。費用の目安は40万円から80万円ほどで、隣地の所有者の立ち会いや同意も必要となるため、時間と手間がかかります。
とくに地方の古い物件では、境界標が失われている、あるいは過去の測量図が残っていないケースも多く、作業が複雑化しやすい点にも注意が必要です。
こちらの記事では、空き家の売却について解説しています。
具体的な方法や流れも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
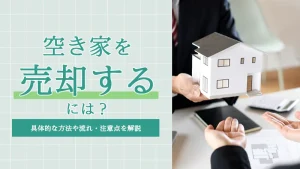
空き家が売れない場合の対処法
空き家がなかなか売れなくても、諦める必要はありません。 原因を正しく整理し、状況に合った方法を選ぶことで、売却のチャンスは十分にあります。
ここでは、売れにくい空き家をスムーズに売却へと導くための具体的な対処法を紹介します。
更地にして売り出す
建物の老朽化が進んでいる場合は、空き家を解体して更地として売り出す方法があります。
新築住宅を建てたいと考えている買い手にとって、更地はすぐに建築ができるため魅力的な選択肢です。古い建物が残っていると、買い手が自費で解体しなければならないため、購入をためらうケースが多くなります。
ただし、更地にする際には注意が必要です。建物を取り壊すと、それまで適用されていた「住宅用地の特例」が外れ、固定資産税が最大で6倍に増えることがあります。
また、木造住宅を解体する場合は150万円から300万円程度の費用がかかります。もし解体後にすぐ買い手が見つからなければ、解体費用に加えて高くなった固定資産税の負担が続き、大きな損失となるおそれがあります。
そのため、更地にするかどうかを決める際は、複数の不動産会社に相談し、売却の見込みや地域の需要を確認したうえで慎重に判断することが大切です。
出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621264.pdf)
リフォームして売り出す
古い空き家をリフォームして、見た目や使い勝手を改善したうえで売り出す方法もあります。
床材や壁紙の張り替え、水回り設備の交換、外壁の塗り替えなどを行うことで、建物の印象は大きく変わります。簡単なリフォームであれば数十万円から始められますが、全面的に改修する場合は1,000万円を超えることもあります。
ただし、リフォームには費用対効果のリスクがあります。売主が「よくなる」と思って行ったリフォームが、買い手の好みに合わないこともあります。とくに、自分でリフォームしたいと考えている人にとっては、すでにリフォーム済みの物件はかえって魅力が下がる場合もあります。
また、立地条件が悪い場合は、どれだけリフォームしても買い手が見つからないこともあります。建物をきれいにしても、駅から遠い、周辺に商業施設が少ないなどの問題は解消できないためです。
リフォームを検討する際は、必ず不動産会社や専門家に相談し、リフォーム費用に見合う売却効果があるかどうかを確認したうえで実施することが大切です。
売り出し価格を見直す
空き家が売れない原因として最も多いのは、売り出し価格が高すぎることです。
首都圏の中古戸建てでは、売り出し価格と実際の成約価格に大きな差が出る傾向があります。多くの購入者は「価格が適正だったから」という理由で購入を決めるため、相場とかけ離れた価格を付けてしまうと、問い合わせ自体が減少してしまう可能性があります。
思い入れのある実家には特別な価値を感じますが、市場は感情を評価に含めません。周辺の成約事例や不動産ポータルに掲載された相場を確認し、現実的な価格に調整して売れやすさを高めましょう。
なお、一度値下げすると再び値上げに踏み切ることが難しくなります。安易に大幅な値下げを行わず、不動産会社の担当者と相談して根拠のある価格を設定してください。
隣地や地権者に売る
空き家の売却先として、隣の土地の所有者に相談するのは意外と効果的な方法です。
「隣地は高くても買え」という不動産の格言があるように、隣地を購入することには多くのメリットがあります。土地の形が整い(整形地化)、接道条件が改善されるほか、敷地が広がることで駐車場や庭などの活用の幅も広がります。
また「知らない人に隣の土地を買われたくない」という理由から、防衛的な目的で購入を検討する人も少なくありません。隣地所有者と良好な関係がある場合は、まず一度相談してみる価値があります。
ただし、個人同士で直接売買を行うと、後々トラブルに発展するおそれがあります。契約書の作成や登記などは不動産会社を介し、正式な手続きを経て進めることが大切です。
不動産会社を変える
今の不動産会社で売却がうまく進んでいない場合は、思い切って別の会社に依頼するのも有効な方法です。
不動産会社には、それぞれ得意とするエリアや物件の種類があります。たとえば、都心の新築マンション販売を得意とする会社に、地方の古い戸建ての売却を依頼しても、効果的な販売活動が期待できないことがあります。
一方で、空き家の売却に特化した会社や、地域の事情に詳しい地元密着型の会社であれば、独自のネットワークを活かして買い手を見つけやすくなります。
とくに、老朽化した家や事故物件など、いわゆる「訳あり物件」の扱いに慣れている専門業者なら、スムーズに売却できる可能性が高まります。
複数の不動産会社に査定を依頼し、物件の特徴をしっかり理解したうえで、販売戦略を具体的に提案してくれる会社を選ぶことが大切です。
不動産の買取業者に依頼する
売れない空き家を確実に、そして早く手放したい場合は、不動産の買取業者に依頼するのが最も効率的な方法です。
買取業者は、空き家を直接買い取り、その後リフォームや再販を行って利益を得る仕組みを持っています。そのため、一般の買い手が見つからないような物件でも買い取ってもらえる可能性があります。
最大のメリットは、売却までのスピードです。仲介による売却では、買い手が見つかるまで数か月から1年以上かかることもありますが、買取業者であれば最短で数日から1か月ほどで現金化できます。
また、仲介手数料が不要なうえに、リフォーム費用や残置物の処理費用も業者が負担します。雨漏りや傾きなどの不具合がある物件でも、現状のまま売却できるため、売主の負担を大幅に減らすことが可能です。
さらに、契約不適合責任が免除されるケースが多く、売却後に建物の欠陥が見つかってもトラブルになる心配がありません。
立地が悪い、築年数が古い、再建築不可、境界不明といった一般には売却が難しい物件でも、専門の買取業者であれば対応できる場合があります。空き家買取に特化した業者は、物件の再活用ノウハウを豊富に持っており、他社に断られた物件でも買い取ってもらえる可能性があります。
空き家バンクに登録する
自治体が運営する「空き家バンク」に登録するのも、売却方法のひとつです。
空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい人と、購入または賃貸を希望する人をつなぐ無料のマッチングサービスです。主に地方移住や田舎暮らしを希望する人に向けて、物件情報を発信できます。
登録料は基本的に無料で、自治体によってはリフォーム費用や解体費用の補助金制度を利用できる場合もあります。ただし、空き家バンクは地域によって利用者数に差があり、登録したからといって必ず買い手が見つかるわけではありません。
また、売買契約の手続きは自分で進めるか、自治体が紹介する不動産会社を通じて行うことになります。場合によっては対応に時間がかかることもあります。
そのため、売却を急いでいない場合や、ほかの方法と並行して活用したい場合におすすめです。一方で、できるだけ早く現金化したい方には、買取業者への売却のほうが適しています。
自治体などに寄付する
自治体や公益法人に空き家を寄付するという方法もありますが、現実的には非常に難しいのが実情です。
自治体が空き家を引き取ると、固定資産税の収入が減るうえに、維持・管理のコストが発生します。そのため、自治体が空き家の寄付を受け入れるケースはごくわずかです。
寄付が認められるのは、公共施設の建設や地域活性化など、明確な公共目的がある場合に限られます。また、多くのケースでは建物が残っている状態では寄付できず、あらかじめ解体して更地にする必要があります。
認可地縁団体(自治会や町内会)に寄付することも可能ですが、これも厳しい要件があり、実際に受け入れられるのはまれです。
そのため、寄付という方法は、特別な事情や公共的な活用の見込みがない限り、現実的な空き家の処分手段とは言えません。
相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した土地を国に引き取ってもらえる制度です。相続した土地の管理や税金の負担に困っている人にとって、手放す手段のひとつとなります。
ただし、この制度を利用するためには非常に厳しい条件があります。建物が残っている場合は必ず解体しなければならず、さらに抵当権が設定されていないこと、土壌汚染や埋設物がないこと、境界が明確であることなど、多くの要件を満たす必要があります。
また、土地を国に引き取ってもらう際には、その土地を維持・管理するために必要とされる10年分の費用にあたる「負担金」を支払わなければなりません。解体費用と合わせると、合計で数百万円の出費になるケースもあります。
手続きも複雑で審査も厳しいため、多くの空き家所有者にとって現実的な選択肢とは言えません。費用を支払って土地を手放すよりも、専門の買取業者に売却したほうが確実で、さらに売却代金を得られる点で有利です。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
売れない空き家を放置するリスク
空き家を長期間放置してしまうと、さまざまなリスクが発生します。時間が経つほど建物の劣化や管理の負担が増え、最終的には多額の修繕費や撤去費用がかかったり、行政から法的措置を受けたりする可能性もあります。
株式会社NEXERとINTERIQによる調査では、空き家の所有者を対象にした約7割が「維持管理の負担が大きい」と感じており、約5割が「精神的なストレスを感じている」と回答しています。
調査データ引用元:記事公開後、該当URLをご記載ください。
固定資産税の支払いに加え、草刈りや清掃などの管理費用、近隣住民への配慮などが重なり、多くの人が経済的・心理的な負担を抱えているのが現状です。
維持費がかさむ
空き家は誰も住んでいなくても、所有しているだけでさまざまな費用が発生します。
最も負担が大きいのは固定資産税で、年間に数万円から十数万円を毎年支払う必要があります。さらに、電気や水道の基本料金、遠方にある場合の交通費、定期的な清掃や草刈りの費用などもかかります。
空き家管理サービスを利用する場合は、月額5,000円から3万円程度の委託費が必要になります。こうした費用が積み重なると、10年間で数百万円に達することもあります。
誰も使っていない不動産にこれだけの費用を払い続けるのは、経済的にも大きな負担です。できるだけ早めに売却や活用を検討することが、無駄な支出を抑える第一歩になります。
管理する手間が発生する
空き家は、放置せず定期的に管理することが欠かせません。
人が住まなくなると、建物の劣化は想像以上に早く進みます。換気をしないことで湿気がこもり、カビや腐食の原因になります。雨漏りや破損箇所を放置すれば、被害が広がり、修繕に高額な費用がかかることもあります。
また、庭の草木を放置すると雑草が伸び放題になり、害虫の発生源になるほか、不審者の侵入や不法投棄といったトラブルのリスクも高まります。
とくに空き家が自宅から遠い場所にある場合は、定期的に訪れて点検や掃除を行うだけでも大きな負担です。年齢を重ねるにつれて、こうした管理作業を続けることはさらに難しくなります。
近隣に迷惑がかかる
管理が行き届かない空き家は、周囲の住民にさまざまな迷惑をかける原因になります。
●老朽化した建物が倒壊した場合:隣家や通行人に被害を与えるおそれがあります。
●害虫やネズミなどの害獣が発生した場合:近隣の住宅にも被害が及ぶことがあります。
●庭の雑草が伸び放題になった場合:景観を損ね、地域全体の環境悪化にもつながります。
●不審者の侵入や不法投棄などが起きた場合:犯罪の温床になる危険性もあります。
こうした問題が続くと、近隣住民からの苦情や通報が増え、所有者自身の精神的な負担も大きくなります。
特定空き家に指定される場合がある
空き家を適切に管理せず放置すると、自治体から「特定空き家」に指定されるリスクがあります。特定空き家とは、倒壊の危険がある、衛生上有害である、景観を著しく損なっているなど、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家を指します。
指定されると土地の固定資産税が上がる
特定空き家に指定され、自治体から改善の勧告を受けると、これまで適用されていた「住宅用地の特例」が解除されます。
この特例が外れると、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がります。たとえば、年間10万円だった固定資産税が60万円になることもあり、経済的な負担は非常に大きくなります。
さらに、2023年の法改正で「管理不全空き家」という新しい区分が追加されました。これは、特定空き家に該当するほど危険ではないものの、管理が行き届いていない空き家を指します。
この段階でも、状況によっては固定資産税の優遇措置が解除される可能性があるため、早めの管理・対応が重要です。
出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621264.pdf)
放置すると罰せられる可能性がある
自治体から改善命令を受けたにもかかわらず、必要な対応を行わずに放置を続けると、50万円以下の過料が課される場合があります。
解体費用を請求される
行政代執行によって空き家が強制的に解体された場合、その費用はすべて所有者に請求されます。
解体費用は建物の規模や構造によって異なりますが、数百万円から1,000万円近くにのぼることもあります。もし支払えない場合は、給料や財産が差し押さえられる可能性があります。さらに、この支払い義務は自己破産しても免除されません。
国土交通省の資料によると、特定空き家に指定された後に行政代執行へと進むケースは年々増えています。空き家を放置し続けることで、想定以上の経済的負担を背負うリスクがあるため、早めの対処が必要です。
空き家を売る前にやっておくこと
空き家の売却をスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。以下の4つのポイントを確認しておきましょう。
境界を明確にしておく
土地の境界をはっきりさせておくことは、空き家を売却するうえでの基本です。
一般的に、戸建てや宅地を売却する際は、すべての境界が確定していることが求められます。境界があいまいなままでは、購入後に隣地とのトラブルが起こる可能性があるため、買い手は購入をためらう傾向があります。
境界が確定しているかどうかは、法務局で「地積測量図」を取得することで確認できます。もし確定していない場合は、土地家屋調査士に依頼して測量を行い、隣地所有者の立ち会いと同意を得たうえで境界を確定させます。
費用は一般的に40万円から80万円ほどかかりますが、専門の買取業者に売却する場合は、売主がこの費用を負担しなくてよいケースもあります。売却をスムーズに進めるためにも、早めの確認と対応を行うことが大切です。
相続登記をする
相続によって空き家を取得した場合、売却前に必ず相続登記を完了させる必要があります。
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。名義が被相続人のままでは、法律上、売却することができません。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続の開始を知ってから3年以内に登記しなければなりません。期限内に登記しないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記の手続きは自分で行うこともできますが、書類に不備があると手続きが遅れます。とくに空き家が遠方にある場合は、司法書士に依頼した方がスムーズです。
空き家の名義が共有なら同意をもらう
空き家が複数人の共有名義になっている場合は、売却するために所有者全員の合意が必要です。
相続によって不動産を取得した場合、法定相続分に応じて共有名義となるのが一般的です。たとえば相続人が3人いれば、それぞれが3分の1ずつの所有権を持つことになります。
共有名義の不動産を売却するには、全員が売却に同意し、売買契約書に署名・押印しなければなりません。1人でも反対する人がいれば、売却は成立しません。
もし共有者の中に売却に反対する人がいる場合は、自分の持分だけを売却することも可能です。ただし、持分だけを購入する一般の買い手は少ないため、こうしたケースでは専門の買取業者に相談するのが現実的です。
共有状態をそのまま放置すると、次の世代に相続が発生した際に権利関係がさらに複雑化します。トラブルを防ぐためにも、早めに共有者全員で話し合い、売却方針を決めておくことが大切です。
解体するかの確認をする
空き家を解体してから売るのか、建物を残したまま売るのかは、慎重に判断する必要があります。
まずは複数の不動産会社に相談して意見を聞き、解体を勧められた場合はその理由と根拠を確認します。解体後に本当に売れる見込みがあるのか、具体的な査定価格や想定期間まで確認すると判断しやすくなります。
安易に解体すると、高額な解体費用が発生し、固定資産税も増える可能性があります。解体後に売れ残ると、費用負担だけが残って大きな損失につながります。
建物の状態や立地、需要を総合的に評価してもらうため、専門業者による査定を依頼してください。なお、専門の買取業者に売却する場合は解体せずに現状のまま手放せるため、費用や手間を抑えられます。
こちらの記事では、空き家の査定方法について解説しています。
査定のポイントや注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
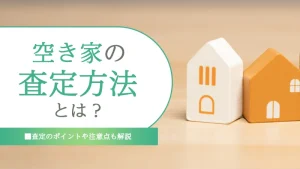
空き家の処分で使える補助金制度
空き家の処分には多くの費用がかかりますが、国や自治体が用意している補助金制度を活用できる場合があります。
空き家の増加は社会問題となっており、国や自治体は対策を積極的に進めています。老朽化した空き家の倒壊を防ぎ、景観や治安を改善し、所有者の費用負担を軽減するために、さまざまな補助金制度が設けられています。
補助金には、国が実施しているものと各自治体が実施しているものがあります。自治体によって制度の有無や内容が大きく異なるため、お住まいの地域の制度を確認することが非常に重要です。
具体的な事例として、東京都の複数の区では解体費用の一部を補助しています。大田区では、老朽化した木造住宅の解体に最大100万円の補助金が出ます。豊島区でも同様の制度があり、解体費用の一部が助成されます。
適用条件
補助金を受けるには、各自治体が定める条件を満たす必要があります。
●市町村税を滞納していないこと
●解体工事を始める前に申請していること
●自治体内に所在地のある解体業者へ工事を依頼すること
改修工事の場合は、台所・壁・屋根など、補助の対象となる工事箇所があらかじめ指定されているケースもあります。
補助金は多くの場合、工事完了後に支給されます。
そのため、一時的に解体費用を全額立て替える必要があり、まとまった資金を用意できないと利用が難しいことがあります。
さらに、申請から交付決定、工事の実施、実績報告、補助金の請求、そして入金までには、複数の手続きと時間が必要です。
売れない空き家に関するよくある質問
空き家の売却や処分について、多くの方が抱く疑問にお答えします。
住まない実家は相続しないほうがいい?
実家を相続するかどうかは、慎重に判断する必要があります。
相続放棄をすると、空き家だけでなく、故人が残したすべての財産を相続できなくなります。預貯金や株式、不動産などのプラスの財産も一切受け取ることができません。
また、相続放棄をしてもすぐに管理責任から解放されるわけではありません。次の相続人が管理を引き継ぐまで、または裁判所が「相続財産清算人」を選任するまでの間は、空き家の管理義務が残ります。
明らかに借金などのマイナス財産が多い場合や、相続人同士で深刻なトラブルがある場合を除いて、安易に相続放棄を選ぶのはおすすめできません。
一度相続してから、専門の買取業者に早めに売却する方が、確実かつ現実的な解決方法といえるでしょう。
出典:E-GOV法令検索「民法940条」(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_4-Se_3-At_940)
空き家の相続放棄はできる?
相続放棄は可能ですが、空き家だけを放棄することはできません。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。しかし、前述の通り、すべての財産を放棄することになり、管理責任もすぐには消えません。
さらに、相続人全員が相続放棄した場合、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があり、数十万円から百万円程度の予納金がかかります。選任までに1年近くかかることもあり、その間は管理を続けなければなりません。
相続放棄は、手続きに時間と費用がかかるうえ、ほかの財産もすべて失うことになります。
そのため、特別な事情がない限りは、一度相続してから売却する方がおすすめです。
田舎の空き家は売れにくい?
田舎の空き家は、確かに都市部と比べて売却が難しい傾向にあります。
人口が少なく、すでに持ち家がある世帯が多いため、中古住宅の需要が限られています。交通の便が悪く、生活に不便な立地では、買い手を見つけるのはさらに困難です。
ただし、田舎の空き家でも、その地域に精通した不動産会社に相談すれば、売却の可能性は高まります。とくに、訳あり物件の買取を得意とする専門業者であれば、立地に関わらず買い取ってもらえます。
田舎の空き家を相続して困っている場合は、地域の実情を理解している業者や、全国対応の買取専門業者に相談することをおすすめします。
1年以上売れないこともある?
空き家が1年以上売れないケースは珍しくありません。
一般的な不動産の売却期間は3か月から6か月程度とされていますが、これは立地や条件がよい物件の場合です。立地が悪い、建物が古い、再建築不可といった問題を抱える空き家は、数年経っても売れ残ることがあります。
長期間売れない場合は、売り出し価格の見直しや、不動産会社の変更を検討すべきです。それでも売れない場合は、専門の買取業者に相談することで、確実かつ迅速に売却できます。
まとめ
空き家が売れない主な理由には、立地条件の悪さや建物の老朽化、再建築ができない土地、境界線があいまいなことなど、さまざまな要因があります。しかし、原因を正しく理解し、状況に合った対処法を選べば、どんな空き家でも手放すことは可能です。
空き家を放置すると、維持費や税金の負担が増えるだけでなく、近隣トラブルや倒壊リスクなどの問題も発生します。最悪の場合、自治体から「特定空き家」に指定され、高額な修繕費や解体費用を負担することになるおそれもあります。
売却方法には、価格の見直し、リフォーム、更地化などさまざまな選択肢がありますが、確実に早期売却を目指すなら、専門の買取業者に依頼するのが最も現実的で安心です。
INTERIQでは、雨漏りや傾きのある物件、老朽化した建物、立地条件が悪い物件でも、現状のまま買い取ることが可能です。仲介手数料やリフォーム費用がかからず、スピーディーな現金化を実現します。
他社で断られた空き家や「訳あり物件」でも豊富な買取実績があり、売却後のトラブルもありません。固定資産税や管理の手間、近隣への気遣いから解放され、心身ともにすっきりとした新しい生活を始められます。
空き家の処分でお悩みの方は、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。