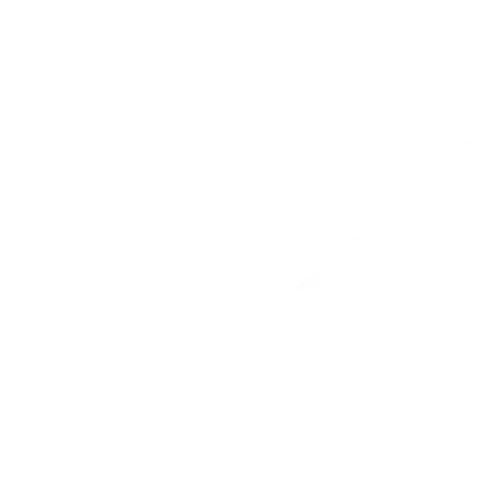不動産手続きのため、住所の正式な表記を知りたいこともあるでしょう。
相続した不動産を登記・売却する場合には、地番での住所表記を使わなければなりません。
本記事では、正式な住所を調べる具体的な手順について解説していきます。
住所には2つの表記がある

「住居表示」と「地番」
私たちが普段使っている住所には、「住居表示」と「地番」2つがあります。
住居表示は、建物の位置ごとに付与される番号で、町名+街区+住居番号の形となります。(例:東京都○○区△△町1丁目2番3号)
一方、地番は土地ごとに割り当てられる番号です。
例えば「東京都○○区△△町1234番地」のような表記で土地の区画を示しています。
住居表示制度の歴史
住居表示制度は、1962年(昭和37年)5月10日に施行された「住居表示に関する法律」に基づいて導入されました。
制定される以前は、住所として土地の地番が使われていましたが、地番は土地の登記を目的に付けられた番号なので、実際の建物や道路の位置とは必ずしも一致していませんでした。
例えば、「123番地」の隣に「456番地」があるといったように、番号の並びに規則性がなく、訪問者や宅配業者、緊急車両が目的地を探す際に混乱が生じていたのです。
この問題を解消するため、建物の出入口の位置を基準として街区を区切り、街区符号と住居番号を付ける仕組みとして住居表示制度が整備されました。
ただし、住居表示制度は主に都市部を中心に実施されており、全国すべての地域で導入されているわけではありません。
現在でも、地方や農村部などでは従来どおり地番を住所として用いている地域もあります。
住居表示と番地の使い分け
住居表示と番地は、用途によって使い分けます。
住居表示を使う場面
・郵便物や宅配便の送付
・住民票や印鑑証明書
・日常生活全般
地番を使う場面
・不動産の登記申請
・土地・建物の売買契約
・相続手続き
・固定資産税の納税
特に不動産に関する法的手続きでは、必ず地番が必要になります。
住居表示しか分からない場合は、地番を調べる必要があります。
【住居表示】正式な住所を調べる方法

住居表示のを調べる方法です。
住民票
住民票に記載されている住所は、住民基本台帳法に基づいて正式に登録された住所であり、公的な手続きにおいて信頼性の高い住所情報です。
住民票には現在の住所だけでなく、前住所も記載されているため、転居履歴の確認も可能です。
住民票を取得するためには、現住所を管轄する市区町村役場に申し出ます。
平日の開庁時間内であれば窓口で申請できますが、多くの自治体では土日や夜間でも取得可能なコンビニ交付サービスを導入しています。
窓口で申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、手数料300円を支払います。
本人確認書類としては、運転免許証・パスポート・健康保険証などが必要です。
コンビニ交付を利用する場合は、マイナンバーカードの提示が必須です。
代理人が申請する場合は、委任状と代理人本人の確認書類を追加で提出しなければなりません。
交付は通常、申請当日に受け取れますが、混雑状況によっては多少時間がかかる場合があります。
郵便物
過去に届いた郵便物から、現在の住居表示を確認できます。
税務署からの納税通知書、年金事務所からの年金関係書類、市区町村からの選挙関連通知などには、住民基本台帳に登録されている住所が記載されています。
ただし、引越し後に郵便の転送サービスを利用している場合は、郵便物の住所が旧住所のままになっていることがあります。
このため、最新の住所を確認するには、直近に届いた官公庁からの郵便物を参照するのが確実です。
インターネットサービス
インターネット上で利用できる様々な住所検索サービスから住居表示を確認できます。
公的データベースと連携しているものから、地図情報と組み合わせたものまで多岐にわたります。
郵便番号検索サービスは、日本郵便が提供する公式サービスで、郵便番号から正式な住所を調べられます。
住所から郵便番号を調べることも可能で、書類作成時の住所表記確認に重宝するでしょう。
住所の表記ゆれや略称にも対応しており、「○丁目○番○号」と「○-○-○」の両方の表記で検索できる利便性があります。
Google マップやYahoo!地図などの地図サービスでは、住所検索機能と航空写真を組み合わせて、建物や周辺環境と照らし合わせながら住所を確認できます。
特に新築物件や住居表示が変更された地域では、最新の情報が反映されていることが多いため住所の正確性を判断する際に有効です。
【地番】正式な住所を調べる方法

納税通知書
固定資産税の納税通知書は、地番を確認する最も手軽な方法の一つです。
毎年4月から6月頃に市区町村から送られてくる納税通知書には「課税明細書」が同封されており、そこに不動産の所在地が地番で表記されています。
例えば「○○町123番4」といった形で記載されているため、住居表示とは異なる表記になっていることが分かります。
複数の不動産を所有している場合は、それぞれの地番が一覧で確認できるため、非常に便利です。
納税通知書は再発行できないため、届いたら大切に保管しておくことをおすすめします。
紛失した場合、市区町村の税務課で「固定資産税評価証明書」や「名寄帳」を取得すれば、同様に地番を確認することができます。
手数料は1通300円程度です。
登記識別情報通知書
不動産を取得した際に法務局から交付される登記識別情報通知書(旧権利証)にも、地番が明記されています。
登記識別情報通知書は不動産の所有権を証明する重要な書類であり、売買や相続で不動産を取得した際に必ず受け取るものです。
登記識別情報通知書には、土地であれば「所在」と「地番」が、建物であれば「所在」と「家屋番号」が正確に記載されています。
表紙をめくった内側のページに詳細な情報が印字されているため、確認してみましょう。
登記識別情報通知書(旧権利証)は非常に重要な書類であり、再発行は原則としてできません。
不動産の権利を証明するためだけでなく、将来的な売却や担保設定の際にも必ず必要となります。
万が一紛失した場合は、法務局で登記簿を取得して地番を確認し、別の手続きで本人確認を行わなければなりません。
法務局
法務局では、住居表示から地番を教えてもらうことができます。
問い合わせる際は、不動産の所在地を管轄する法務局に連絡します。
管轄が分からない場合は、法務局のウェブサイトで検索するか、最寄りの法務局に相談すれば案内してもらえます。
電話口で住居表示を伝えると、担当者がデータベースで検索し、該当する地番を教えてくれます。
もちろん、窓口を訪れて直接確認することも可能です。
法務局にあるブルーマップを使えば、住居表示で場所を特定した後、その土地の地番を地図上で確認できます。
青色で印字された数字が地番を示しており、土地の形状や隣接する土地との関係も把握できるため、不動産の位置関係を理解するのに役立ちます。
ブルーマップは法務局では無料で閲覧できますが、購入する場合は1冊2万円~と高額です。
頻繁に地番を調べる必要がある不動産業者などは購入していますが、個人で一度だけ確認したい場合は、法務局や図書館での閲覧がおすすめです。
公図を閲覧
公図とは、土地の位置や形状、地番を示した図面で、法務局で管理されている公的な資料です。
地番を確認するだけでなく、土地の境界や隣地との関係を把握するのにも役立ちます。
公図は法務局の窓口またはオンラインで取得できます。
窓口申請の場合、おおよその所在地を伝えれば、該当する公図を閲覧させてもらえます。
手数料は1枚450円で、コピーを取得することも可能です。
公図には各土地の地番が数字で記載されており、土地の形や配置が分かりやすく図示されています。
ただし、公図は測量図ではないため、正確な面積や境界を示すものではありません。
あくまで地番と土地のおおよその位置関係を確認するための資料として活用しましょう。
相続や売買で正確な境界が必要な場合は、別途測量が必要になります。
まとめ
正式な住所を調べる方法についてお伝えしました。
個人の現住所確認には住民票が最も確実で、不動産の詳細情報には登記簿謄本が適しています。
インターネット検索は手軽さが魅力ですが、公的手続きでは必ず正式な書類での確認が必要です。
重要な契約や申請の前には、必ず公的書類で住所を確認する習慣をつけることをおすすめします。
INTERIQでは、お客様の状況や物件の特性を把握し、最適なご提案をいたします。お見積もり・ご相談は無償で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。