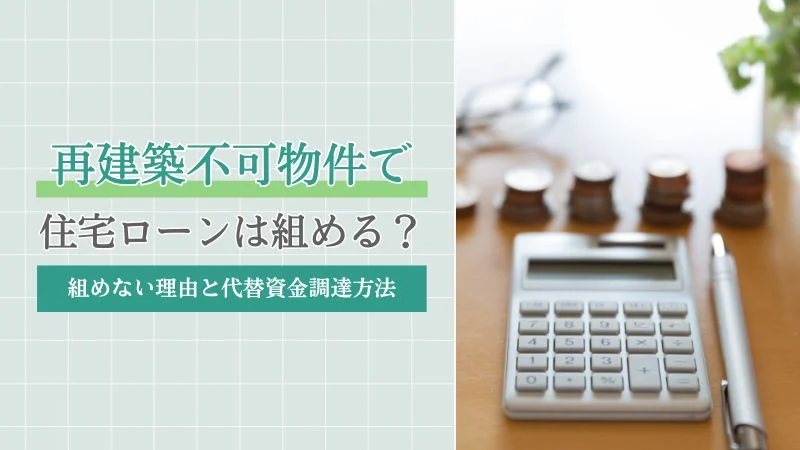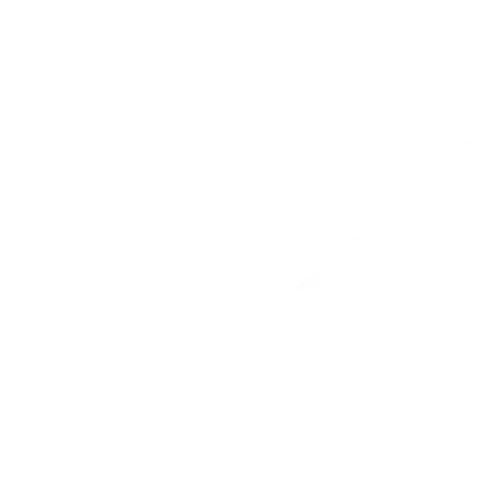再建築不可物件は市場価格より安く購入できる魅力がありますが、住宅ローンの利用可否が大きな懸念材料です。
結論として、一般的な住宅ローンの利用は極めて困難であると言わざるを得ません。
しかしながら、条件次第でローンが組めるケースやその他の代替手段が存在します。
本記事では、再建築不可物件における資金調達をする際の解決策について解説します。
再建築不可物件で住宅ローンが組めない理由

再建築不可物件において一般的な住宅ローンが組めないのはどのような理由からでしょうか。
物件の将来性
金融機関が住宅ローンを提供する際に重視するのは、「返済が滞った場合に物件を売却して融資額を回収できるか」という点です。
再建築不可物件は、この回収可能性において大きな課題を抱えています。
建物が老朽化した際に建て替えができないため、将来的な資産価値の維持が困難になるからです。
通常の住宅であれば、建物が古くなっても土地の上に新しい建物を建てられるため、土地の価値がある程度保たれます。
しかし再建築不可物件は、建築基準法の接道義務を満たしていないなどの理由から、既存建物を解体すると新たな建物が建てられません。
通常の住宅なら適切なメンテナンスにより資産価値をある程度維持できますが、再建築不可物件は建物の寿命が尽きれば資産価値がほぼゼロに近づきます。
この「将来的な価値消失の確実性」が、金融機関にとって受け入れ難いリスクとなっています。
特に返済期間が20年、30年と長期にわたる住宅ローンでは、返済期間中に建物価値が大幅に減少することが確実視されるため、融資判断において重大なマイナス要因となるのです。
流動性リスク
金融機関が再建築不可物件への融資を避けるもう一つの理由は、流動性リスクです。
流動性リスクとは、必要な時に物件を速やかに売却できるかどうかのリスクを指します。
再建築不可物件は購入希望者が限られるため、売却に時間を要し、希望価格での売却も困難なことから流動性が高いとは言えません。
借主が返済不能となり、金融機関が物件を差し押さえて売却しようとしても、買い手が限定的であり、融資額を回収できないリスクが高いのです。
どうしても住宅ローンを利用したいとき

再建築不可物件を購入する場合、一般的な住宅ローンは利用が難しく、仮に融資が下りても高金利や借入期間の制限など、条件面で不利になります。
しかし、一定の条件を満たして「建築可能な土地」に再生できれば、通常の住宅ローンが利用できるケースもあります。
ここでは、再建築不可物件を再建築可能にする4つの代表的な方法を解説します。
方法①隣地を購入または借りて接道条件を満たす
建築基準法では、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していることが建築の基本条件です。
したがって、道路との接道幅が2mに満たない土地は、原則として再建築ができません。
このような場合は、隣接地を買い取るか、一部を借り受けることで接道条件を満たす方法があります。
たとえば、旗竿地や路地奥の土地で、間口が1.5mほどしかない場合でも、隣地の一部を取得すれば接道幅を2m以上に拡張できます。
また、土地の一部を譲り合う「等価交換」によっても接道義務をクリアできるケースがあります。
売買ではなく、隣地の一部を提供し、代わりに同じ面積を譲り受ける方法です。
なお、こうした対応を行うには隣地所有者との合意が前提になります。
契約書の作成や登記変更を伴うため、専門家(司法書士・土地家屋調査士)に相談しながら進めるのが一般的です。
方法②セットバックで道路幅を確保する
敷地が2m以上の接道を持っていても、道路自体の幅が4m未満である場合、再建築にはセットバック(敷地後退)が必要です。
セットバックとは、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることで、将来的に道路幅を確保する制度です。
対象となるのは以下のような道路です。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 2項道路 | 建築基準法施行前から存在する狭い道路で、セットバックが必要な道路 |
| 位置指定道路 | 行政が建築用道路として指定した私道 |
| 協定通路 | 私道の所有者同士が通行協定を結んでいる道路 |
セットバック工事には40万〜100万円程度の費用がかかるのが一般的です。
ただし、後退した部分は道路扱いとなるため、自分の敷地から除外され、建ぺい率や容積率にも影響します。
方法③道路の位置指定を申請する
接している通路が建築基準法上の道路に該当しない場合、自治体へ「位置指定道路」の認可申請を行うことで、再建築が可能になる場合があります。
位置指定道路とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、個人所有の通路を行政が正式な道路として認める制度です。
申請が認められるには、自治体によって細部は異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。
- ・幅員が4m以上あること
- ・境界線が明確であること
- ・排水設備が整備されていること
- ・両端が公道や他の道路につながっていること(行き止まりの場合は長さ35m以下)
- ・関係地権者の承諾を得ていること
位置指定の手続きには図面作成や測量が伴うため、土地家屋調査士や行政書士の関与が一般的です。
方法④但し書き道路の許可を申請する
接道している道路が法的に認められていない場合でも、建築基準法第43条但し書きに基づき、「建築審査会の許可」を得れば再建築が可能になります。
この申請は、「当該敷地への交通上・安全上の支障がない」「近隣の生活環境に支障がない」と判断されれば認められることがあります。
但し書き道路の許可は自治体の裁量が大きく、地域によって審査基準が異なるのが特徴です。
また、建築士による事前相談や図面提出が必要なこともあります。
再建築不可物件の代替資金調達方法

一般的な住宅ローンが利用できない場合でも、再建築不可物件を購入するための資金調達方法は存在します。
ここでは実際に活用できる代替手段について、それぞれの特徴と注意点を解説します。
不動産担保ローン
不動産担保ローンは、再建築不可物件の購入において現実的な選択肢の一つです。
住宅ローンが自宅購入や増改築など不動産関連の用途に限定されるのに対し、不動産担保ローンは資金使途が自由で、生活費や事業資金、納税資金など幅広い目的に利用できます。
不動産担保ローンは、すでに所有している不動産を担保として資金を借り入れる仕組みです。
所有している自宅や投資用不動産などを担保に入れることで、再建築不可物件の購入資金を調達できます。
例えば、相続で取得した実家を担保に入れて、都心の再建築不可物件を購入するといったケースが考えられます。
金利は住宅ローンより高いものの、無担保ローンに比べれば低く設定されており、年利3%から8%程度が一般的です。
ただし、融資額は担保評価によって決まるため、担保物件の価値が低い場合は十分な額を借り入れできない可能性があります。
不動産担保ローンを提供する金融機関には、銀行だけでなくノンバンク系の金融会社も含まれます。
ノンバンク系は審査が比較的柔軟で、銀行で断られた場合でも融資を受けられることがありますが、金利は銀行よりも高めに設定されることが多く、年利5%から10%程度になることもあります。
不動産担保ローンは金利が高めで、返済期間も一般に10年程度と短いことが多い点には注意が必要です。
ノンバンクローン
ノンバンクローンとは、銀行以外の金融機関が提供するローンのことです。
ノンバンクは預金業務を行わず、融資や与信業務に特化した金融機関で、信販会社、消費者金融、クレジットカード会社などが代表的な例として挙げられます。
ノンバンクローンの主な特徴は、銀行ローンに比べて審査が迅速で手続きが簡単なことです。
WEBでの申し込みが可能で、スピーディーに融資を受けられるケースが多い点もメリットと言えます。
ただし、金利は銀行ローンより高めに設定されることが多く、借入可能額も少ない傾向があります。
ノンバンクは貸金業法の下で営業しており、総量規制(借入総額が年収の3分の1まで)が適用される点も特徴です。
ノンバンクローンと銀行の大きな違いは、預金を扱わずに貸付業務のみに特化している点です。
利用者にとっては手続きが簡便で借りやすい反面、金利負担がやや高くなるという特徴があります。
フリーローン
フリーローンは使途を限定しない個人向けローンです。
借入可能額は一般的に500万円から1,000万円程度が上限となることが多く、大型物件の購入には不十分な場合があります。
しかし、小規模な再建築不可物件や、自己資金と組み合わせての購入であれば活用できることもあるでしょう。
フリーローンの金利は年利5%から15%程度で、無担保であることから比較的高めに設定されています。
審査は収入や勤続年数などの個人属性が中心となり、物件の担保評価は行われません。そのため、物件の種類に関係なく利用できる点がメリットです。
返済期間は5年から10年程度が一般的で、短期間での完済を前提とした資金計画が必要になります。
自己資金での購入を検討する際のポイント

ここでは自己資金での購入を選択する際の判断基準と、注意すべきポイントを解説します。
再建築不可物件は市場価格より安価なケースが多いため、小規模な物件であれば自己資金での購入も現実的な選択肢となります。
自己資金での購入をおすすめする最大の理由は、金利負担がないことです。
融資を利用する場合、元本に加えて利息を支払う必要がありますが、自己資金であればその負担がありません。
例えば、1000万円の物件を金利5%で10年返済のローンを組んだ場合、総支払額は約1270万円となり、270万円もの利息を支払うことになります。
利息負担がないことは、長期的な資産形成において大きなアドバンテージとなります。
また、融資を利用しないことで審査の手間や時間も省けます。
金融機関との交渉や書類準備に時間を費やすことなく、売主との条件交渉に集中できます。
現金購入は売主にとっても魅力的です。融資特約による契約解除のリスクがないため、売主は安心して取引を進められます。
その結果、価格交渉において有利な立場に立てることもあります。
実際、現金購入を条件に物件価格から5%から10%程度の値引きを引き出せるケースも珍しくありません。
しかし注意すべき点もあります。自己資金のすべてを物件購入に充ててしまうと、急な出費や生活資金に対応できなくなるリスクがあります。
最低でも生活費の半年分から1年分程度は手元に残しておくべきです。
また、再建築不可物件は購入後にリフォームやメンテナンスが必要になることが多く、その費用も考慮する必要があります。
築年数が古い物件であれば、購入価格の20%から30%程度のリフォーム費用を見込んでおくと安心です。
投資目的で購入する場合は、その資金を他の投資に回した場合の利回りと、再建築不可物件からの賃料収入を比較検討することが重要です。
年利5%で運用できる投資商品があるなら、それと再建築不可物件の実質利回りを比較し、どちらがより効率的な資産運用かを判断する必要があります。
再建築不可物件購入時の資金計画の立て方

ここでは、失敗しない資金計画の具体的な立て方を解説します。
実際に再建築不可物件の購入を進める際は、綿密な資金計画が不可欠です。
通常の不動産購入以上に、様々なリスクや追加費用を想定した計画を立てる必要があります。
まず最初に行うべきは、総必要資金の正確な把握です。
物件価格だけでなく、諸費用も含めた総額を算出します。
不動産取得には、仲介手数料、登記費用、不動産取得税、固定資産税の精算金などがかかります。
物件価格の7%から10%程度を見込む必要があり、例えば1000万円の物件であれば、70万円から100万円の諸費用が発生します。
再建築不可物件の場合、購入後すぐにリフォームが必要になることも多いため、その費用も初期費用として組み込むべきです。
次に、資金調達方法を具体的に決定します。
自己資金がいくらあり、不足分をどのように調達するかを明確にします。
例えば、物件価格1000万円、諸費用100万円、リフォーム費用300万円で総額1400万円が必要な場合、自己資金800万円、不動産担保ローン600万円という具合に資金の出所を明確化します。
融資を利用する場合は、月々の返済額が家計や事業収支を圧迫しないか、慎重にシミュレーションしましょう。
投資用として購入する場合は、収支計画も重要です。想定賃料収入から、ローン返済額、管理費、修繕積立金、固定資産税、保険料などの経費を差し引いた実質収支を計算します。
再建築不可物件は将来的な建て替えができないため、修繕費用を通常より多めに見積もることが賢明です。
目安として年間賃料収入の10%から15%程度を修繕費として確保しておくとよいでしょう。
また、空室リスクも考慮し、年間想定賃料収入の10%から20%程度を空室損として見込んでおくべきです。
最後に、出口戦略も資金計画に含めます。
再建築不可物件は将来的な売却が困難になる可能性があるため、何年保有するのか、その期間でどれだけのキャッシュフローを得られるのかを計画します。
例えば10年保有する場合、10年間の累計キャッシュフローと、10年後の予想売却価格を合わせた総リターンを算出し、投資判断の材料とします。
購入時の価格から10年後に30%から50%程度価値が下がることを想定した保守的な計画を立てることで、予想外の損失を避けられます。
まとめ
再建築不可物件で住宅ローンを組むことは、一般的な不動産購入と比べて確かに困難です。
金融機関は担保価値の低さと流動性リスクを理由に、融資に慎重な姿勢を取ります。
しかし本記事で解説したように融資を受けられる可能性も存在します。
住宅ローンが難しい場合でも、不動産担保ローンやビジネスローン、フリーローンといった代替手段があります。
それぞれ金利や条件は異なりますが、自分の状況に合った方法を選択することで資金調達は可能です。
再建築不可物件は比較的安価であることから、自己資金での購入も現実的な選択肢となるでしょう。
大切なことは、物件価格だけでなく諸費用やリフォーム費用を含めた総資金を正確に把握し、返済計画や収支計画を慎重に立てることです。
再建築不可物件は将来的な価値減少が避けられないため、保守的な資金計画と出口戦略が必要です。
まずは複数の金融機関に相談し、自分の状況で利用できる融資方法を確認することから始めましょう。
INTERIQでは、お客様の状況や物件の特性を把握し、最適なご提案をいたします。お見積もり・ご相談は無償で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。